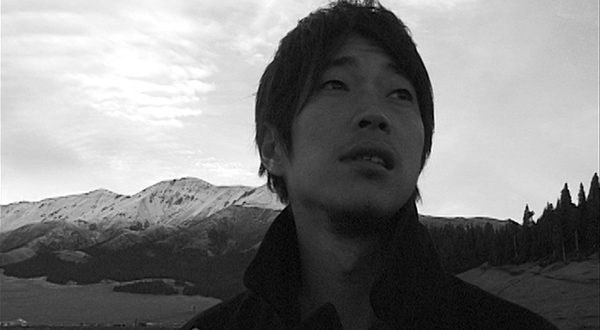第488回 「収容病棟」

トークに臨むワン・ビン監督(右)と戌井昭人さん(配給のムヴィオラ提供)
昨年のベネチア国際映画祭でワールドプレミアされた王兵(ワン・ビン)監督の最新作「収容病棟」の特別上映と監督も参加するトークイベントが先日、恵比寿映像祭の中で行われた。
大雪で交通が混乱する中、成田空港から駆けつけたワン・ビン監督はいつもの穏やかな語り口で作品の魅力と撮影スタイルへのこだわりを披露してくれた。
トークは小説家、脚本家で俳優でもある戌井昭人さんが質問する形で進められた。最初に戌井さんが「こちらが見ているのではなく、自分がそこ(収容病棟)にいるみたいな感じで、それがまだ続いている気がします」と感想を語ると、監督は「みなさんが映画の中に入りこんで、精神病院の中の生活を登場する人たちと一緒に経験して行くというリアルな感覚を持っていただいていい」と答えた。
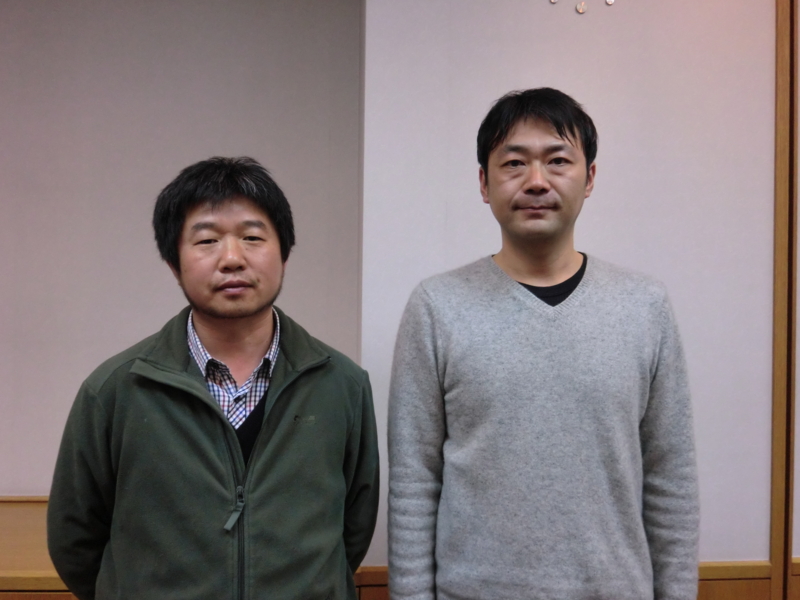
ワン・ビン監督(左)と戌井昭人さん(同)
ワン・ビン監督の作品には「無言歌」や「三姉妹~雲南の子」など食べる印象的なシーンが多い。そこを聞かれ、監督は「食べて寝るという人間としての基本的な営みを映画で描いています。いろいろな人の食べるシーンを通じてその姿をとらえています」と説明する。
人を見つめ表現するという共通点のある戌井さんが「ワン・ビンさんはどういう顔をしてカメラを構えているでしょうか。笑っているのか、すごく無表情なのか、あるいは感動しながら撮っているのでしょうか」と“変化球”を投げると、監督は「緊張しないでリラックスしてカメラを構えることにしています。映画は観客をどう映像の世界に連れていくかが課題。現場の生き生きしたものを映像で伝えていくのが映画なので、気楽な気持ちで撮るようにしています。そうすれば撮るべき人物の日常生活が撮れます」と生真面目に答えた。

「収容病棟」の一場面 (C) Wang Bing and Y. Production
そうは言っても最初緊張していたことは事実。カメラを回す人は監督ともう一人いて、監督が回している時、外の廊下にいたもう一人が患者から暴力を振るわれることが1回だけあった。この患者は翌日「昨日は病気の具合が悪く、殴ってしまって申し訳ない」と謝りに来たという。時間が経つうちに監督はもちろん、周りの方も“侵入者”の存在に慣れてきて普段の生活を取り戻し、監督たちは病院の中で3カ月撮り続けることができた。
撮影をするきっかけは「鉄西区」の編集が終わりかけた2002年秋、北京郊外の精神病棟を偶然見かけたことから。開放された門からは誰も姿が見えず、中に入っていくと、4、5棟には20、30年も閉じ込められている患者がいた。すでに戸籍も病院に移され、引き取り手の家族もいない人たちだった。興味を持ち撮影を持ちかけたが許可が下りず、12年になって知人を通じ雲南省の精神病院から許可が下りて、13年正月から撮り始めた。

「収容病棟」の一場面 (C) Wang Bing and Y. Production
死ぬまで病院に居続ける人たちについて監督は「人が生きるということはそれぞれ違う運命を背負っていくことです。映画を見るということは自分が経験したことのない他者の人生を経験することに他なりません。そこが映画の面白さです」と語った。
会場の参加者からも影響を受けた映画や小説の有無を聞かれ、「あらかじめ予期された範囲で物語を作り上げていく映画の撮り方を放棄するという流れが90年代から2000年にかけて出てきました。私も偶然性の中で映画を撮るのは好みに合ったので、そのように目の前の人物を見るという習慣が段々身につき、自分なりのスタイルを作り上げていきました」と振り返った。
会場からは「収容者が200人ということですが、主要な登場者はどういう観点から選びましたか」という質問も。
それに答え監督は「リサーチなしで撮っていきました。いろいろな人物を撮っていきながら映画全体の構成を決めていくというスタイルです。ある時は拒絶されました。そんな時は無理をせず撮影を放棄していく。撮りながら自然に選択して行きました」。
出てくる人はみな印象深い。個性が際立っていると言った方が相応しいかもしれない。監督も「それぞれ特徴があって生き生きとしている。ただそういう人が持っている悲劇性とか生命力といったものは往々にして気付かないことが多い。でもひとりひとりの人間には物語があって、映画の中で言葉や行為が積み重なっていくと、ある人物の個性的な顔が見えてくるのです」と解説する。
最後に監督は「この物語に登場する人たちは今も映画で描かれたような生活を続けています。ですからその小さなプロットを心の中に留めて、ぜひこの映画を覚えていてください。そしていろんな人物に注目を払っていただきたいと思います」と締めくくった。
監督の要望を聞かずとも、人間本来の姿を素朴にリアルに表現する人たちの濃密な227分を共有すれば、彼らを忘れられるはずはない。
「収容病棟」は6月、シアター・イメージフォーラムほか全国順次公開【紀平重成】