特集:泣ける映画3選
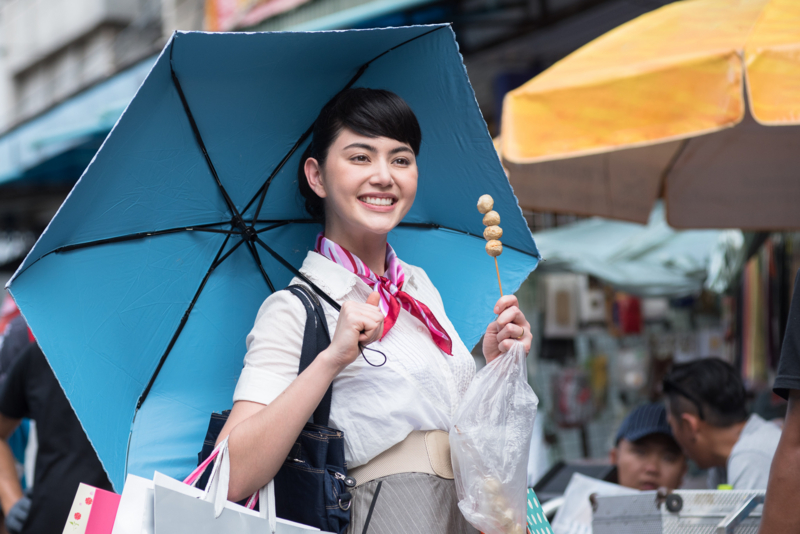
「突然20歳 タイの怪しい彼女」のワンシーン
泣ける映画が良い映画かどうかは別にして、劇中人物への感情移入が高じ、思わず落涙してしまうことがある。そんな時、自分が感動する作品に出合えたことを心から喜ぶとともに、アジア的精神風土とでもいうべき共通する感覚に触れたのではないかと思うことがある。韓国映画「怪しい彼女」(ファン・ドンヒョク監督)のリメイクである「突然20歳 タイの怪しい彼女」(アーラヤ・スリハーン監督)を見たときも、オリジナルと同じ場面で感情が高まり、涙をこらえることができなかった(本ブログでは第620回で紹介)。

「突然20歳 タイの怪しい彼女」のワンシーン
その場面を紹介しよう。偶然20歳に若返った主人公のおばあちゃんが、夫不在で苦労した青春を取り戻そうと、身分を隠し孫のバンドのボーカルとして大活躍。しかし大事なコンサートの当日、孫が交通事故で意識不明の重体に陥り、おばあちゃんは血液型の一致する孫のために輸血を受け入れ、手術室に入ろうとする。そんな彼女が実は自分の母親だと知った息子が、「お母さんには苦労をかけた。どうか自分の青春を大事にしてほしい」と背後から声をかける。
ファンタジーだから実際にはあり得ない展開ながら、泣かされてしまうのはなぜか。「ああここで泣いたぞ」と原作を思い出し、最初から泣きモードに入ってしまうのか。それともこの言葉が入れば必ず観客は泣きだすという「キラーワード」が混じっていたのだろうか。あるいは同じアジア人同士、子が親の長年の労苦をしのびつつ、さらなる心遣いに感謝するというパターンはアジア共通の涙を誘うメンタリティなのかもしれない。
ちなみにタイのリメイク版が日本初上映となった大阪アジアン映画祭の上映後のQ&Aで、監督は「他の人のために、家族のために生きるというタイ人の価値観を付け加えた」と話していたが、まさにこの言葉こそアジアの倫理観と言えないだろうか。
リメイク許諾の版権を持つ韓国の映画製作会社CJの機密情報ロッカーには人を泣かせる「キラーワード」の秘伝が収納されているのかもと考えるのは楽しい。またリメイクがアジアではなく欧米で実現したときに、どのような脚本が用意されるか想像するのも興味深い。

「小さな園の大きな奇跡」のワンシーン
泣ける映画の2つ目は「小さな園の大きな奇跡」(本ブログでは第606回で紹介)。これは観客もさることながら、監督が制作過程で先に泣いてしまったというから相当だ。
この映画は実話が元になっている。有名幼稚園の園長を辞したルイ(ミリアム・ヨン)は、ある日、幼稚園の園長募集のニュースを見かける。園児はわずか5人。一人でも欠ければ園は閉鎖される。しかも給料はわずか6万円で…というストーリー。2015年の香港における興行成績でトップ10入りした。
日本公開を前に、筆者が監督に出演した俳優とのやり取りを尋ねた際の答え。
「ルイス・クーさんと初めて会ったとき、素敵なオフィスに行って、30分ぐらいこの映画について話をしたのですが、後に彼から聞いた話によると、最初の5分しか話が分からなかったよ、と。残りの25分は私の言っていることがちんぷんかんぷんだったと。なぜなら僕がずっと泣き続けていたから(笑)。でも監督がこれほど感動しているのならきっといい映画になるだろうと。結局、なんの質問もなくそのやりとりは終わりました。だから情熱っていうのは大事だなって思います」
監督の人柄を伝えるエピソードなので、再掲載させていただいた。そして筆者のインタビュー中も目に涙を浮かべ、撮影中のエピソードを一生懸命紹介してくれたことを報告しておく。

エイドリアン・クワン監督(右)と共同脚本家のハンナ・チャンさん (2016年10月6日、東京・新宿で筆者写す)
小さな子供達に泣いてもらうために涙ぐましい努力を払ったことも印象的だった。
「私にとって一番大変だったのはメイチュ役の子が涙を流すシーンです。何が一番怖いの? 想像してごらん、と言ったら、空を飛ぶ蛇がいたら怖いと言うので、じゃあ空に蛇が飛んでいるところを想像してごらん、と言ったんです。手を差し伸べて雨に触れるシーンは何百回も行いました。手を差し伸べるだけではなくて、恐怖を感じているのだということを伝えました。彼女は幸福な家庭で育っているので親を失うなんて想像したこともない。私は自分の母親を10年ぐらい前に亡くしているので、自分の経験を語って聞かせました。ですからこのシークエンスを見るたびに母を亡くした話を思い出し、個人的には非常に苦しいシーンです」
プロデューサーを引き受けたベニー・チャン監督は「エイドリアン・クワンは、とても情熱的でこどものような無邪気さをもった監督だ。自分が関わった映画の中で、自己犠牲の愛を描いたこの映画は、この数年で最も意味があるものだと思っている」と評価する。
泣ける映画の3つ目は「おばあちゃんの夢中恋人」(本ブログ第542回で紹介)。大阪アジアン映画祭とシネマート六本木の閉館サヨナラ特別企画「台湾シネマ・コレクション2015」で上映された作品(北村豊晴、シャオ・リーショウの共同監督)だ。
病院に運ばれ一命をとりとめた祖父に、18歳の孫が映画脚本家だった祖父と女優だった祖母とのなれそめを聞き始める。
台湾語映画の売れっ子脚本家の劉奇生(ラン・ジェンロン)は大スターの万宝龍(ワン・ボーチエ)の熱烈なファンである蒋美月(アン・シンヤ)と知り合う。彼女の明るく無邪気で一途な性格にひかれた奇生は、社長の借金を肩代わりすることを条件に監督を任され、美月を主役に抜擢するが……。
認知症で夫のことも分からなくなった美月が徘徊で行方不明になった際、奇生は思い出の場所を探し出し愛妻を発見する。そして夫婦だけしか知らない会話をかわすことで妻は昔を思い出して行く。老夫婦の会話がかつての若いカップルの映像と交差し、奇跡が起きる展開に観客は感動しないではいられないであろう。

「おばあちゃんの夢中恋人」のワンシーン
認知症の人が昔を回想することで病状の進行を遅らせたり記憶を少しずつ取り戻して行くことはよく知られており、回想法と呼ばれる。中でも昔の童謡や写真、映画はそのための小道具として効果があるという研究があり、どちらもよく利用される。その認知症と映画という極めて相性のいい組み合わせをそっくり脚本に取り込んだアイデアがすばらしい。
認知症になったら嫌だなと考える人はどこの国でも多いが、認知症になってもこんな素敵なことがあればいいなと思わせるなかなかいい作品なのである。
ご紹介が長くなってしまったので今回は3選としたが、他にも紹介したい映画がたくさんある。期日を改め第2弾として特集したいと考えている。どうぞご期待ください。












