第638回 「日曜日の散歩者 わすれられた台湾詩人たち」のホアン・ヤーリー監督に聞く
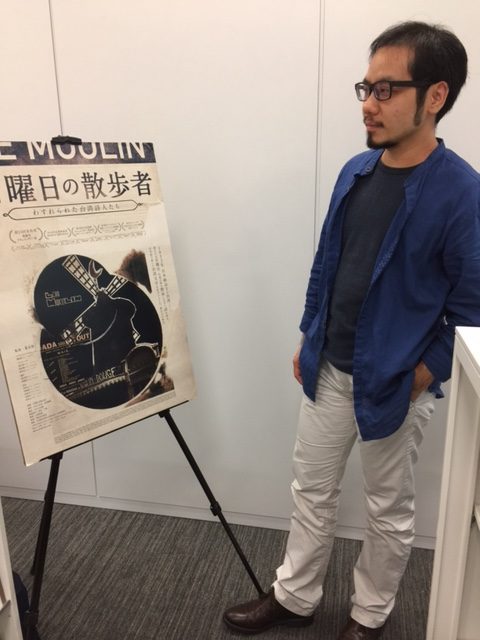
ホアン・ヤーリー監督(2017年7月18日、東京都港区虎ノ門の台湾文化センターで筆者写す)
1930年代、日本の統治が始まって40年近くたった台湾の古都・台南に西洋モダニズム文学の波が押し寄せた。支配者の言葉である日本語で新しい台湾文学を生み出そうとした台南の詩人団体「風車詩社」のメンバーは、戦後の政治弾圧事件などで日本語を禁じられ迫害されていく。だが、時代の渦の中に埋もれていった彼らに突然光が当たる。詩の朗読や古い写真、そして文字資料が織りなす詩的な映像から、詩人たちの創作意欲や悲しみが伝わってくる。ホアン・ヤーリー監督に聞いた。
--「風車詩社」の存在を知った時の感動をご紹介ください。
「その時まで風車詩社のことを全く知りませんでした。台湾は国民党政権が長かったので、教科書もステレオタイプで、日本の統治時代の記述が少なく、南京大虐殺しか載ってないという感じでした。でも台湾から見ると南京は大陸のことなので、その時代に台湾はどうだったのかという事は全く分かりませんでした。ところが今はネット時代です。いろいろなことを調べたら、ある日突然、風車詩社に関する論文が私の目の前に現れたのです。それを読んでびっくりしました。とても面白い。台湾の30年代にはなんとこんな人たちがいて、しかも当時はやっていた文化、芸術といったものを取り入れようとしていた。いかに自分が台湾のことを知らなかったかという事の現れですね。それが衝撃的でした」

風車詩社のメンバー (C)2015 Roots Fims Fisfisa Media All Rights Reserved.
--その風車詩社は1933年に台南で生まれました。取材や撮影を通じて、なぜ台南だったのかと思われませんでしたか? 台北や台中ではなくて……
「この問題はあまり議論されていませんでした。日本の大東和重関西学院大学教授(比較文学)の論文によると、台南は文化の伝承が盛んな古都で独特の風情があります。一方当時の台湾では日本人と台湾人が文学などクリエイティブな面で友情を結ぶことが多かったといいます。たとえば当時台湾には『民俗台湾』という雑誌があり、日本人が中心になってやっていたのですが、台湾人も研究に参加していました。その雑誌は台南に関する関心が強く、盛んに調査研究が行われたといいます。台南というのは文化芸術の盛んな街で、文化人たちは台南に対して独自の想像力を働かせ、あるいは愛着の思いを寄せました。パリや東京と同じように、そこに暮らしている人の独自な観察力、あるいは切り口でもって、知られていない台南の何かを発掘しようとする人たちがいたのだと思います。風車詩社の詩人たちも日曜日に台南の街を散歩しながら詩を語ったのでしょう。
--同じ台南出身でヤン・クイ(楊逵)という「新聞配達夫」を書いたプロレタリア文学者がいます。
「ヤン・クイは当時流行した左翼文学の影響を受けて、その世界に進みます」

ムーランルージュ (C)2015 Roots Fims Fisfisa Media All Rights Reserved.
--またもう一人リウ・ナオウ(劉吶鴎)という人も台南出身で、一時プロレタリア文学に関わります。ですから、いろいろな思想が生まれる土壌があったという事でしょうか? そして日本や大陸へ行く……。
「リウ・ナオウのことは、ある学者に聞きました。彼は何故風車詩社の人たちと交流がなかったのかと。するとその学者は、1930年代当時は交通が発達していなくて、また共通の友人もなく、知り合う機会はなかったのだろうと言います。リウはのちに東京の大学で学び、また上海にも行って、彼の手掛けた作品は風車詩社と全く路線が違います。リウはフランス語ができ映画を撮ったりと何でもできる人です。彼にとっては上海に行けば何でも条件がそろうことになるのです。一方風車詩社は月下美人のように夜花が咲いて一瞬のうちに消えていくはかない存在だったのではないでしょうか。彼らは日本から戻るとずっと台南にとどまったのです。ですから台南に対しては文句が多くなります。作品をよく読んでみると、台南文壇の議論はいつも活気がない、閉鎖的で自由ではない。展覧会は年2、3回しかやっていない、こんなところがどうやって発展するのかという話がいっぱい出てきます。結局、上海は都市型特有のモダニズムであり、台南は非常に純朴で古い都ですから、都市型のモダニズムは向いていない。けれどもそこにいる詩人たちは自分たちの暮らしている街を一生懸命研究し、地方特有の色合いにプラスして特殊なモダン的要素を掘り出していこうと考えていたかもしれません」
--先ほど国民党の教育のせいで知らない歴史がいっぱいあったと話しましたが、ウェイ・ダーション監督も台湾の昔のことを調べて、「セデック・バレ」「KANO~1931海の向こうの甲子園~」のような映画を制作しています。一方、ホアン監督はまた別の方法で昔の台湾から面白いものを発掘しています。そこに共通性を感じます。
「ウェイ・ダーション監督の作品、特に日本とのかかわりのある作品は私も見ました。『KANO~1931海の向こうの甲子園~』を見てわかるように、いま台湾では大勢の人が、日本統治下の台湾では日本人がいろいろな面で貢献したという事を知っています。今まで知っていることと映画の中で描かれていることとの違いがどうだったのかを考えるのにすごくいい材料でした。わたしの映画もそうですが、映画を見た後に観客の皆さんとある種のインタラクティブな交流ができるといいです。私は映画の中で何も説明していませんが、映画を見た人は自分で考えて探究すればいいと思います。日本とのかかわりで言うと『湾生回家』という懐古映画もありました。ともかくテーマがたくさんあって、それぞれがバラバラで破片みたいなものですが、少なくともこういった破片を通して、台湾の歴史を我々は考えなければいけない。また過去だけにこだわるのではなく、未来に向かって、じゃあどうなるのという事を絶えず考えればいい。私も今回日本に来て、台湾のあの時代のことを皆さんはどう思いますか、いいですか? それとも悪い?とぜひ聞きたいです。

昭和レトロ? (C)2015 Roots Fims Fisfisa Media All Rights Reserved.
--映画の作り方ですが、詩の朗読、それから写真や絵画の大量使用、そして再現映像、の3つの要素でこの作品を構成されています。それはどうしてですか?
「ドキュメンタリー映画を撮るときには関係者にインタビューし、その映像を流すという事はよくあります。私はインタビュー映像を多用することは嫌いです。実際にはインタビューをたくさんしましたが、映画の中には入れませんでした。なぜなら権威ある人からコメントや解説を聞いて、なるほどと理解を深めるわけですが、そのやり方はすでに確立されているので、あえてこのやり方を取らなければどうなるかと考えました。権威ある方の映像を取り外すことによって、むしろ映像、音声、あるいは文字を用いて語る際に映画自体が理解される空間の自由度が広くなっていく。つまり解釈は観客に任せるということです。映画は光を使っての表現ですから、光そのものに対しても見る人の受け止め方は千差万別で、全く違って見えます。特に文字で書かれている文献は大体紙です。それを映像を通して見せることは、ひょっとしたら文字そのものは文字ではなくなって、血となり肉となって一つの脈が生まれ、違うものが生まれてくるのではないでしょうか。カット割りを使うことによって文献そのものも成長していくこともあるのではないかと思います。このように見ることによって、観客の皆さんの感覚、思考といったものがどこかで結び付き、違うものを見ることができるのではないでしょうか。実際に映画を見た人が私にこう言いました。2回目に私が見たものは監督が1回目の後に編集し直したのではないですか?と。そこで、いや、そのままなんですよと答えたことがあります。これは、1回目と2回目で見た人の受け止め方が変わり違うものが見えたという事です。こういう映画を撮るときに芸術的にはこうだという説明を排除しようと思います、あくまでも映像、音声、文字、それを使って観客に見せて、観客も自分の想像を超える何かを受け取って、新たに何かを発見するという、ある種の交流ができるのではないかと思います」
--この方式は今回が初めてなのでしょうか?
「長編でドキュメンタリー作品としては今回が初めてです。この前ショート2本を撮っていますが、同じ手法かどうか自分もよくわからない。今回の映画作りで協力してくれた日本人で小川さんという人がいるのですが、彼が言うにはショートも含めて全部同じ手法だと言います(笑)」
--そうすると次回作も同じ手法になりますか?
「次の作品と言ってもいつになるかわかりません。まだ借金をいっぱい抱えているので、それを返さなくてはいけない」
--この制作の内幕という本を書かれては?
「実は風車詩社に関する本を出そうと考えていて、それをやっていたらますます借金が膨らんでしまったんですよ(笑)。提案はなかなかいいので有難うございます(笑)」

挿入されるカット (C)2015 Roots Fims Fisfisa Media All Rights Reserved.
--日本語で創作することへの葛藤が映画の中でも指摘されていますが、その葛藤をよく示すエピソードがありましたら教えていただけますか?
「風車詩社の人たちの生まれた環境を見ればわかるように。彼らはどちらかというと裕福な人たちです。製糖会社の息子や台湾の3大財閥の子弟ら上中流の家庭に育ちました。小さい時から日本語を話す家庭に育ち、日本語は日本人と同じようにうまい。日本語を用いて表現するときにもふさわしい表現ができる。たとえば実験作品を作る、あるいは抒情的な作品を作る、そのどちらも自由自在にできる。でも葛藤はあります。たとえば、台湾のいなか娘を描こうとするときに日本語で書いたほうがより適切か、それとも台湾語で書いたほうがよりいいのではないかというケース。当時は植民地ですから日本語を話さなければならない、でも描く対象は台湾の物語。そこで純粋に芸術性を選ぶか、それとも政治性をとるか、その関係が裏表のようで、片方だけを切り捨てることができない。創作意欲はあるのに植民地で生まれ育ったための矛盾ですね。彼らは周りの人たちに理解されない。なんで台湾人なのにと言われる。彼らは時には孤独で、異邦人のように見られてしまう。もちろん日本語を用いた文学創作そのものを認められたいという気持ちは強いと思いますが、結局は言語とは切っても切れない環境の中に置かれているので、日本語を用いて植民地である台湾を何か書くしかないという事は、ある種の運命と言ってもいい。こういう状況に置かれている文学者の悲しみという部分でもあると思います」
本作品は第53回金馬奨最優秀ドキュメンタリー賞に輝いた。
「日曜日の散歩者 わすれられた台湾詩人たち」は8月19日よりシアター・イメージフォーラムほか全国順次公開【紀平重成】
【関連リンク】













