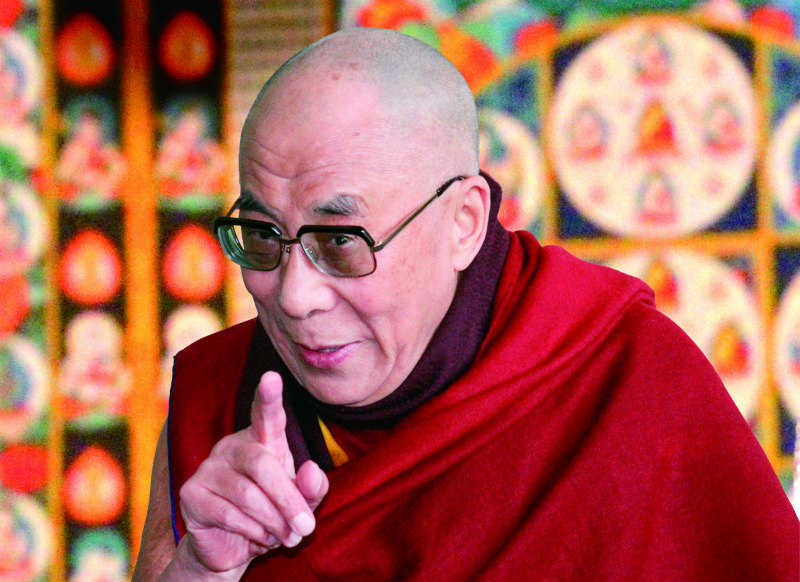第767回「返校 言葉が消えた日」

どの国や地域にも世界に誇りたい歴史があれば、逆に隠しておきたい負の歴史もある。台湾の場合は戒厳令が敷かれた1949年から解除された87年までの「白色テロ」と呼ばれる38年間は触れられたくない時代と言える。この場合、隠しておきたいと考えたのは、中国共産党との内戦に敗れ大陸から渡って来たあと、台湾に一党独裁の圧政を敷いた国民党だ。逆に相互監視と密告を強制された反体制派住民の中には、投獄、処刑までされるという弾圧の嵐が去るのをじっと待つほかは無かった。本作はそんな暗い時代を描いた作品だ。

1962年、戒厳令下にあった台湾では自由を唱える書籍は厳しく禁じられていた。違反者は逮捕され、中には死刑を執行される者もいた。翠華高校3年のファン・レイシンは備品室で密かに行われていた発禁本の読書会メンバーだ。ある日、放課後の教室で目覚めたファンは人の気配が無いことに気付きロウソクをかざしながら校内をさまよい始める。そのうち彼女は1年後輩の男子生徒で自分に好意を持つウェイ・ジョンティンに出合う。同じ読書会メンバーでもあった彼と一緒に出口を探すものの、どうしても外に出ることができない。やがて2人は、なぜ自分たちだけが取り残され他の仲間がいないのか、その理由を深く知ることになる。そこには学校で起きた政府による迫害事件と、原因をつくった密告者の存在が絡んでいた。

台湾にはこの時代を描いた『悲情城市』(ホウ・シャオシェン監督、89年)や『クーリンチェ少年殺人事件』(エドワード・ヤン監督、91年)といった傑作がある。が、しかしその名監督に続いて白色テロ時代を描く勇気と才能のある監督は現れなかった。本作のジョン・スー監督は久しぶりに登場した本格派監督ということになるのだろうか。
ただ、スー監督の経歴を見ると長編映画は本作が初めてであり、むしろゲーム作りの技術やセンスが先行している様子がうかがえる。事実、2017年に発売されたホラーゲーム「返校 -Detention-」がいきなり大ヒットし、それをもとに実写映画化された本作は19年の興行記録ナンバーワンとなった。エンターテインメント作品として作られたとしてもゲーム版と映画の制作順序が逆になっていればこれほどヒットしたかどうかは分からない。
それでも映画の前半は主人公のファンとウェイが謎解きに挑むダーク・ミステリーでありながら切ない青春ドラマにもなっている構成には引きつけられてしまう。しかもゲームを堪能する気分で映画を見ていくうちに台湾という小さな島を揺るがせた暗黒時代をリアルに体感できるのだから侮れない。どうやらゲームだけでなく映画の作り方もうまいと言っていいだろう。

そんなスー監督が劇中で読書会を指導するチャン先生に自由の尊さを語らせながら、「生きていれば希望はある」と生徒に諭す場面は監督が最も訴えたかったメッセージであろう。監督がこだわるのは「言論の自由」がいとも簡単に統制され、あるいは自主規制していく事例を数多く目にしているからである。とりわけアジアでは香港の有力日刊紙が廃刊に追いやられるなど言論統制が進み、外国の話と呑気に構えていられる情勢ではなくなった。
スー監督のように「この自由はよりよい未来と引き換えに自身を犠牲にした多くの人たちの苦難の上にもたらされた。当たり前のように思っているこの自由を大切にしなければいけない」との考えから映画に込められたメッセージはきちんと受け止めたい。
近年、台湾ではウェイ・ダーション監督(『セデック・バレ』)やトム・リン監督(『夕霧花園』)らの手で歴史を掘り下げた作品が作られるようになった。「自分たちのルーツを知りたい、知ってほしい」と思うことはごく自然であり、一つの流れとして注目していきたい。

主演の二人についても触れておく。読書会メンバーの高校3年18歳ファン・レイシンを演じたワン・ジンは14歳の時に小説家としてデビュー。チャン先生に恋心を抱く早熟の生徒をごく自然に演じている。今後の活躍が楽しみな女優だ。
その彼女を密かにあこがれる読書会仲間のウェイ・ジョンティンを演じたツォン・ジンファは万単位のオーディションを勝ち抜いた。きりっとした目は間違いなく将来のスター候補生である。
『返校 言葉が消えた日』は7月30日よりTOHOシネマズ シャンテほか全国順次公開【紀平重成】